高齢者の「排泄介助」|在宅介護でのポイントと介助方法

高齢者の排泄介助は、在宅介護で多くのご家族さまが直面する大きな課題のひとつです。
ご家族さまの排泄介助が必要になった際、手順や方法がわからず戸惑う方も多いのではないでしょうか?
また、排泄介助は清潔を保つだけでなく、排泄物や皮膚の変化を観察して体調の異変を早期に察知する役割も担います。
今回は、高齢者の排泄介助の方法やポイントについてご紹介します。
排泄介助とは
排泄介助とは、自力で排泄(尿や便の排出)が難しい方を手助けすることです。
排泄介助は、以下のような内容が含まれます。
- トイレまでの移動の介助
- 適切な体位のための介助
- 尿器や便器の使用の介助
- 排泄後の処理
- 清潔保持
安全かつ効果的に介助するために、排泄障害の種類や排泄介助のポイントを押さえることが大切です。

排泄介助の基本手順と注意点
在宅介護で排泄介助をおこなう際の、基本の手順と注意点についてご紹介します。
排泄介助は、安全を最優先にして、急がせたり、無理をさせたりしないことが基本です。また、排泄後の処理や清潔を保持する場面では、防水シーツ・おしり洗い・使い捨て手袋・保護クリームなどがあると、より介助がしやすくなります。
トイレでの介助手順と注意点
トイレの介助の際には、トイレ周辺のスペースを確保し、動線上の安全を確認します。
トイレまでの移動は相手のペースに合わせ、立ち座りのふらつきによる転倒を防ぐために、手すりをしっかりと握ってもらうなど、安全を確保しながらおこないましょう。

また、ズボンの上げ下ろしやトイレットペーパーの使用など、自分でできる動作はできるだけ任せることで自立性を保つことができます。
緊急時に対応できるよう、鍵はかけずに扉の外で待機しましょう。急がさず、必要なときに声を掛けて確認することが大切です。
ポータブルトイレの介助手順と注意点
ポータブルトイレは車椅子の方や寝たきりの方など、トイレまでの移動が難しい方が使用する移動可能なトイレです。また、夜間の転倒リスクを下げるために、夜間のみポータブルトイレを併用する選択もあります。
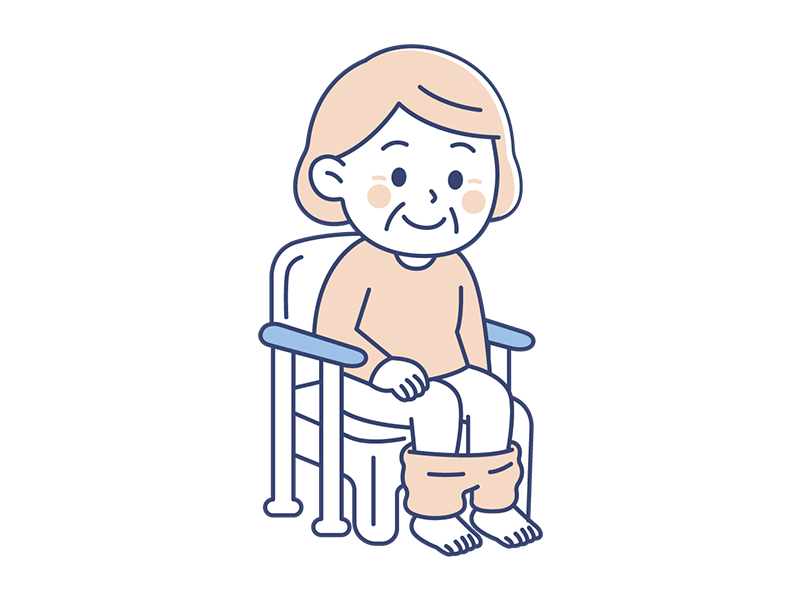
ポータブルトイレには手すりが付いているので、しっかり握ってもらい、安全を確保しましょう。また、排泄前にポータブルトイレの底に紙を敷くと後処理がしやすく、臭い対策にもなります。
おむつを使用する場合の介助手順と注意点
尿失禁や便失禁のある方には、おむつの使用がおすすめです。
サイズは太腿の隙間やギャザーの密着で判断し、交換は便の場合はすぐに、尿の場合はパッド併用でこまめにおこないましょう。

おむつの中に便失禁したままの状態が続くと、皮膚が弱い高齢者は感染や炎症のリスクが高まるため、丁寧な清潔保持が欠かせません。
高齢者の排泄障害が引き起こす心理的な悪影響
高齢者の排泄障害は、心理的な悪影響を引き起こします。これは気持ちの問題にとどまらず、活動量低下や筋力低下など、身体機能の悪化にもつながります。
高齢者によく見られる排泄障害の種類
排泄障害とは排尿障害と排便障害の総称で、尿や便を溜めたり出したりする排泄行為に、何か問題があることをいいます。
以下は排泄障害のひとつである排尿障害です。個々の症状や原因は人によって異なりますが、症状が続いたり、悪化したりする場合は早めに医師へ相談しましょう。
尿失禁
高齢者によく見られる問題で、尿が意図せずに漏れることがあります。これは膀胱や尿道の筋肉の衰えや神経のダメージによるものが多いです。
過活動膀胱
膀胱が過剰に収縮し、頻繁に尿意を感じる状態です。高齢者ではよく見られますが、神経や筋肉の問題によって引き起こされることがあります。
尿路感染症
尿の通り道である尿道口から菌が侵入し、体内で繁殖する感染症の総称です。高齢者は免疫機能が低下しやすいため、尿路感染症にかかりやすく、尿路感染症は排尿障害の一因となることがあります。
排泄障害がもたらす羞恥心・孤立感
排泄は羞恥心を伴うプライベートな行為で、排泄障害が起きると高齢者の自尊心を大きく傷付けてしまうことがあります。
また、排泄の不安から外出を避ける傾向が強まり、社会活動への参加意欲が低下します。 これらの心理的影響は、高齢者の生活の質を低下させるだけでなく、身体的な健康状態にも影響を及ぼす恐れがあるため十分なケアが必要です。
高齢者の排泄障害の対処
尿失禁や過活動膀胱の場合、利尿作用が強いカフェインやアルコールの摂取を控えるほか、膀胱トレーニングや骨盤底筋トレーニングなどのエクササイズが効果的です。これらは、膀胱のコントロールを改善し、尿漏れを減らすのに役立ちます。
生活の中での工夫も大切ですが、尿失禁や過活動膀胱などの排泄障害は、専門家の支援や医師への相談をおすすめします。
排泄介助のポイント
排泄介助は、以下の6つのポイントに注意しておこないましょう。
排泄のタイミングをつかむ
排泄のタイミングをつかむためには、数日の排泄パターンの観察が必要です。
排尿の場合は、水分を摂る時間や何時間後ぐらいに排尿があるかといったタイミングを把握しておくとトイレへの誘導がしやすくなります。
認知症の方は尿意や便意をうまく伝えられない場合があります。
そわそわ歩き回る・椅子から何度も立ち上がるなど、人によって異なるサインを見逃さないことが大切です。
水分摂取量を制限しない
水分摂取量を制限しないようにしましょう。
水分を控えてトイレの頻度を減らそうと考える高齢者は少なくありません。
しかし、体内の水分が不足すると、脱水症や脳梗塞などを引き起こすリスクが高くなるため、十分な注意が必要です。

また、介護を担うのがご家族さまの場合、夜間の排泄介助はご家族さまの睡眠サイクルが乱れるなど、健康に悪影響が及ぶ可能性もあります。日中の水分摂取を促し、夕方以降は控えるなどの工夫をおすすめします。
スキンケアをおこなう
高齢者の肌は乾燥して弱くなっているため、常時おむつを着用するようになると皮膚炎が起こりやすくなります。IAD予防のために、ケアに気を付けましょう。

IAD(Incontinence Associated Dermatitis:失禁関連皮膚炎)
尿または便(あるいは両方)が皮膚に接触することにより生じる皮膚炎です。おむつを常時利用している高齢者にとって問題になるのがこのIADです。
「拭き過ぎ」に気を付ける
おむつを交換する際に、頻繁に拭き過ぎたり強くこすってしまったりすると、皮膚に必要な皮脂を取り過ぎてしまいます。その結果、尿のアンモニアや便の消化酵素による化学的刺激が加わるだけでなく、拭き取る際の物理的な刺激もIADを悪化させる原因になってしまいます。
優しく拭き取るほか、おむつの上で洗い流せて、すすぎの必要がない弱酸性のお尻洗浄剤などもおすすめです。
お尻のケアは「保湿と保護」が必須
「お尻が乾燥しないように、おむつ替えの後はワセリンを塗っている」という方は多いですが、実はスキンケアとしては不十分です。お尻も顔のスキンケアと同様に、保湿が必要です。しっかり保湿剤で保湿した後、ワセリンなどの油脂性の軟膏やクリーム、スプレーなどでカバーするように皮膚を保護しましょう。
これにより、水分を閉じ込めると同時に、排泄物と皮膚の間に「保護膜」ができ、IADの予防につながります。
プライバシーの尊重と羞恥心への配慮
介助中であってもプライバシーを尊重し、ドアを閉め、カーテンを引くなどの配慮が必要です。
トイレの外で排泄が終わるまで待機し、急かさないようにします。
「恥ずかしい」「情けない」といった感情から、水分補給や食事を摂ることを拒んでしまうケースもあるので、排泄介助の際には、羞恥心への配慮が欠かせません。
自尊心を傷付けない
排泄介助をおこなう際に、負担を感じている様子を見せたり、排泄に失敗したときに責めたり批判すると、被介護者である高齢者の自尊心を大きく傷付け、心を閉ざさせてしまうこともあります。

排泄介助は、介護を担うご家族さまにとって肉体的・精神的にも大きな負担となりますが、相手の思いに寄り添いながら思いやりのある声掛けをしていきましょう。
できるだけ本人に任せる
できることはご自身でおこなっていただくことが、身体的な機能や精神的な健康を維持する上で大きな役割を果たします。
自立を促すことは、自己価値感や自己決定権を高め、自己効力感の向上につながります。
専門のサービスを利用する
専門サービスを利用することで、介護の負担を分担・軽減しましょう。
たとえば、当社の訪問看護サービスでは「排泄のケア」「服薬による排便コントロール、摘便や浣腸による排泄の支援」「福祉用具(ポータブルトイレなど)の利用相談」もおこなっています。
そのほかにも、排泄関連のサービスや福祉用具はいくつかあります。
- 訪問介護サービス
- 通所介護サービス
- 自動排泄処理装置のレンタル
- 電動昇降便座のレンタル
- トイレの手すりのレンタル
- ポータブルトイレの購入
ケアマネジャーへの相談
もし家族だけでは問題を解決できないと感じたら、専門家であるケアマネジャーに相談することを検討してみてください。
「いつ・どの場面で失敗しやすいか」「介助者の負担が大きい時間帯」など排泄に関する具体的な問題を整理した上で、伝える内容を事前にメモしておくと相談がスムーズです。
また、トイレの手すりのレンタルやポータブルトイレの購入、手洗い器の設置に伴う改修工事は、介護保険の適用範囲です。高齢者の状態に応じた必要な福祉用具を整えて、ご本人さまとご家族さま、双方の負担を減らしましょう。
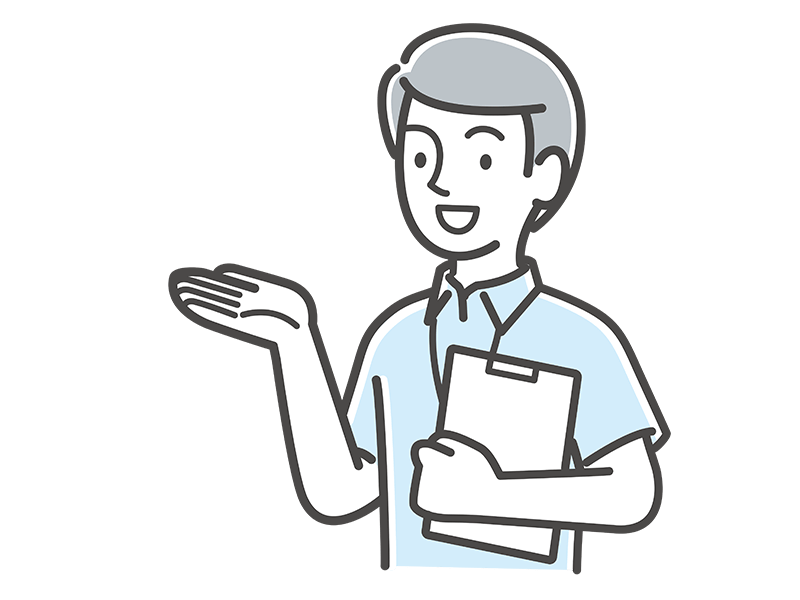
まとめ
排泄介助は、身体的なケアだけでなく、心理的なサポートも必要です。
高齢者の排泄障害は、心理的な悪影響を引き起こす可能性がありますが、適切な介助やコミュニケーションによってその影響を軽減できます。
排泄介助にはさまざまな方法があり、安全性や清潔さを保つポイントに注意しながら個々の希望や能力に応じて適切な介助をすることが重要です。
また、被介護者だけでなく介護者の健康も大切です。ストレスを抱え過ぎないように、訪問看護サービスなども積極的に活用しましょう。
訪問看護や訪問リハビリをお考えなら「DSセルリア」で
「DS訪問看護ステーション」では、病気や障害のある方が住み慣れた地域やご自宅でその人らしい暮らしができるよう、看護師や理学療法士・作業療法士などがご自宅に訪問して、その人にあった看護やリハビリテーションを提供します。
施設見学・ご相談は随時受け付けております
ご自宅での介護に関してお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
DSセルリア株式会社では、東京・千葉エリアにリハビリ型デイサービス「トータルリハセンター」や訪問看護ステーションを設け、地域に根ざした「訪問看護・リハビリテーションサービス」をご提供しています。
また介護従事職にご興味のある方も、お気軽にお問い合わせください。


