褥瘡(じょくそう)への対応で知っておきたい基本知識とケア方法

褥瘡(じょくそう)をご存じですか?
褥瘡は、長時間の圧迫や摩擦によって皮膚が傷付くことで起こり、重症化すると強い痛みや感染を伴うこともあります。しかし、早めの対応と継続的なケアをおこなうことができれば、在宅介護でも十分に予防・管理が可能です。
今回は、褥瘡の基礎知識やご自宅でのケア方法、訪問看護による専門的なサポートなどについて解説します。
目次
褥瘡とは?基本的なメカニズムと原因
褥瘡とは、「床ずれ」ともいわれ、身体の同じ部位に長時間圧力がかかり、皮膚やその下の組織が壊れてしまう状態のことです。
寝たきりの方や車いすで長時間同じ姿勢を保つ方に多く見られるため、在宅介護の方は特に注意が必要です。
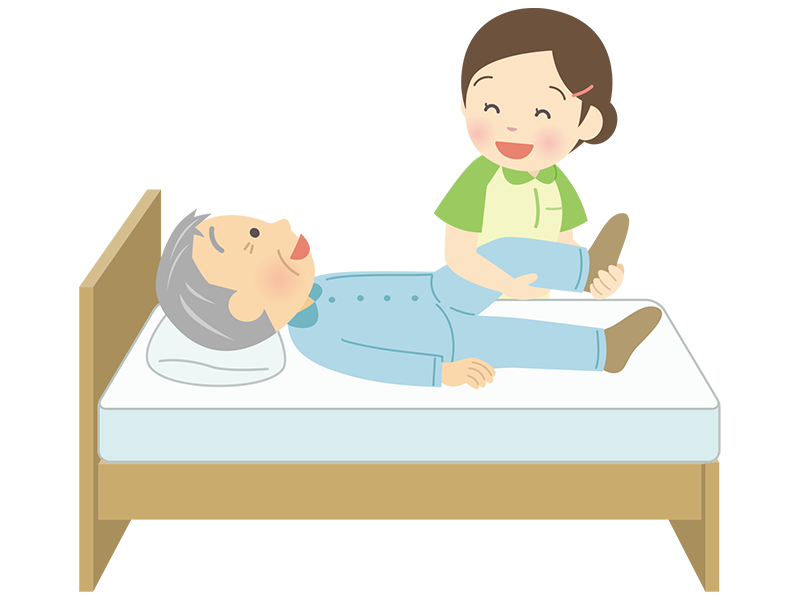
褥瘡が発生する理由
褥瘡は、長時間同じ姿勢でいることで骨の出っ張った部分が圧迫され、その部位の血流が滞ることで発生します。
このような状態が継続すると、圧迫された箇所の細胞に十分な酸素や栄養が届かなくなり、皮膚の奥から損傷が進行します。
寝たきりの方は、自力で体位変換(身体の向きや姿勢を変えること)ができないため圧迫が長時間続くだけでなく、体の「ずれ」やシーツとの「摩擦」、汗や失禁による湿った状態など、さまざまな要因が重なって褥瘡のリスクが高まります。
褥瘡の初期症状
褥瘡は、まず皮膚の赤み(発赤)から始まります。
褥瘡ではない一時的な赤みは、体位を変えると数十分で消えますが、押しても赤みが消えない状態は褥瘡の初期段階です。
感染症を併発するリスクもあるため、圧迫をとっても赤みが消えないと感じたら、早めに医師や訪問看護師などへ相談することが大切です。
褥瘡ができやすい部位とその理由
褥瘡ができやすい部位は、体重が集中的にかかる以下の部位です。
| 仙骨部(せんこつぶ) | お尻の中央にある骨の出っ張りです。仰向けで寝る時間が長い人は、この部位に褥瘡ができやすいです。 |
| 踵(かかと) | 皮膚のすぐ下に骨があるため、クッションとなる筋肉がほとんどなく、褥瘡につながりやすい部位です。 |
| 坐骨部(ざこつぶ)・尾骨部(びこつぶ) | 長時間の座位で圧迫されやすい場所のため、車いすで過ごす時間が長い方によく見られます。 |
| 肩甲骨・後頭部 | やせて筋肉が少ない方の場合、仰向けで寝ている際に圧が集中しやすくなります。 |
| 大転子(だいてんし/腰の横あたり) | 横向きで寝ているときに、片側に圧が集中しやすく、摩擦による皮膚ダメージが起こりやすくなります。 |
| 耳 | 横向きで寝るときに枕と接する部分で、特に耳介(じかい:耳のふち)に圧がかかります。 |
その他に、硬すぎる介護用マットレスや車いすの座面、しわのあるシーツや衣類によって局所に高い圧力と摩擦が集中すると、褥瘡ができやすくなります。
低栄養・血行障害など内的条件
褥瘡の発生には、外からの圧迫や摩擦だけでなく、身体の内側の状態も大きく関係します。
低栄養や脱水が続くと、皮膚や筋肉の弾力が失われ、わずかな圧力や摩擦でも傷付きやすくなります。
また、疾患などが理由の血行障害・むくみ・発汗や失禁による湿潤環境も皮膚のバリア機能を低下させ、褥瘡が発生する要因になります。

ご家族さまがご自宅でできる褥瘡への対応
寝たきりの方や身体が不自由な方の介護をしている場合、褥瘡への正しい対応が重要です。
褥瘡は一度できると治りにくいですが、早期に気付き、正しい対応を積み重ねることで悪化を防ぐことができます。
ここでは、ご自宅でご家族さまができる褥瘡のケア方法と、日常で意識したいポイントを紹介します。

体圧管理と体位変換で圧迫を減らす
褥瘡は、長時間同じ姿勢で過ごすことで、一部に圧力がかかり起こります。
そのため、圧迫を分散させることが最も基本的なケアです。
体圧分散マットレスや車いす用クッションの使用など、圧力が一点に集中しないように工夫することが重要です。ベッドの背もたれや膝の角度を調整するときは膝を先に上げ、背中を一度ベッドから離してずれを防止します。
車いすに長時間座るときは15分ごとに一度尻を浮かせるなど、同じ姿勢が長時間続かないように注意してください。
栄養と水分補給で治癒力を高める
褥瘡ができてしまった場合、皮膚の修復を助けるための栄養補給が欠かせません。低栄養は、褥瘡を悪化させ、感染症のリスクも高めます。
以下のような栄養が含まれる食材を、積極的に摂取しましょう。
- たんぱく質(皮膚や筋肉をつくるのに役立つ):肉・魚・卵・豆腐など
- ビタミンC・亜鉛(皮膚の再生や免疫維持に役立つ):ブロッコリー、柑橘類、牡蠣、牛肉など

また、脱水は血流を悪化させるため、少量ずつでもこまめに水分摂取を心掛けましょう。食事が進まない場合は、補助食品や栄養ドリンクの利用も検討し、医師・看護師・栄養士への相談もおすすめです。
下記のコラムでは、高齢者に多い低栄養について、また栄養の摂取方法などをご紹介しています。
皮膚の清潔維持と保湿ケア
褥瘡ができてしまった場合、患部の感染や悪化を防ぐための清潔管理を丁寧におこないましょう。
汗や排泄物で皮膚がぬれたら、おむつや寝衣をすぐに交換しましょう。洗浄の際は低刺激性の石けんをよく泡立て、手のひらでやさしく洗いましょう。洗浄後は、皮膚の乾燥を防ぐために保湿クリームを薄く塗布します。
失禁などで湿潤が続く部分には、撥水性のあるクリームやスキンバリア材を使用すると、皮膚を守ることができます。

患部の処置
褥瘡の処置は、進行度や滲出液(しんしゅつえき)の量に応じて処置方法が変わります。
自己判断で薬を使うと悪化することもあるため、基本的には医師や訪問看護師の指示に従いましょう。
赤みや傷が浅い段階の場合にはワセリンや軟膏を薄く塗布し、皮膚を保護します。軟膏を塗布する際は、患部の周囲を撥水クリームでカバーした上で、ガーゼなどのテープが皮膚に食い込まないように貼ることが大切です。
ポリウレタンフィルムなどのドレッシング材は湿潤環境を保ちながら痛みを緩和するので、初期の褥瘡に有効です。
皮膚の赤み、水泡、浸出液、発熱、痛みなどの異常を感じたら医師に連絡し、病院で診察を受けましょう。
訪問看護による褥瘡への対応
寝たきりの方やお体が不自由な方がご家族さまにいる場合、「褥瘡への適切な対応をおこなう」ことも重要ですが、「褥瘡ができないように備える」ことも大切です。
そのためには、早い段階から医師や訪問看護師などの専門職と連携し、皮膚の状態や生活環境を継続的にチェックしてもらうことが効果的です。
訪問看護師などの看護師は褥瘡のリスク評価をおこない、正確に把握した皮膚の状態を踏まえてご家族さまにも分かりやすく観察のコツを説明し、日々のチェック体制を一緒に整えていきます。
DSセルリアでも、福祉用具(ベッド・ポータブルトイレ・補聴器・車いす・食器など)の利用相談、体位交換、関節などの運動や動かし方の指導などさまざまな支援をおこなっています。
褥瘡の発生を防ぐ生活習慣と環境づくり
専門家と連携しながら、日常的にスキンケア・体圧・栄養管理を続けると、褥瘡の発生リスクは大幅に減らせます。介護の負担がある場合や専門的なことがわからない場合は、訪問介護や訪問看護などのサービスを利用し、ご家族さまだけで抱え込まないことが何よりも大切です。
早期発見を可能にする毎日の皮膚チェック
褥瘡の初期は、赤みやわずかな違和感から始まることが多いため、毎日の観察が何より重要です。
- 朝と夜の2回を目安に、全身の皮膚をやさしく観察する
- 皮膚を押しても赤みが消えない部位がないかを確認する
- 汗や排泄物で湿っている、身体の部位がないかを確認する
こうしたチェックを習慣化することで、早期対応につながり、重症化を防げます。
体圧分散と体位変換で「圧」を逃がす
車いす用の体圧分散クッションの利用、体位変換などをおこない、同じ場所に圧がかかり続けないよう気を付けましょう。
介護保険でレンタルできるエアマットレスやクッション、介護リフトなどもあるため、ケアマネジャーや訪問看護のスタッフに相談することをおすすめします。

まとめ
褥瘡は毎日の皮膚観察、体位変換、栄養管理などでリスクを減らすことができます。しかし、ご家族さまだけで抱え込むと負担が大きいため、専門家の支援を受けることも大切です。
東京・千葉エリアで訪問看護をおこなうDSセルリアなら、看護師がご自宅で処置・体位変換指導などさまざまなサポートが可能です。褥瘡の予防やケアでお困りの際は、ぜひお気軽にセルリアの訪問看護サービスへご相談ください。
高齢者の歩行で気になることがあれば「DSセルリア」へ
当社では、訪問看護を提供しています。
「DS訪問看護ステーション」では、病気や障害のある方が住み慣れた地域やご自宅でその人らしい暮らしができるよう、看護師や理学療法士・作業療法士などがご自宅に訪問して、その人にあった看護やリハビリテーションを提供します。
施設見学・ご相談は随時受け付けております
ご自宅での介護に関してお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
DSセルリア株式会社では、東京・千葉エリアにリハビリ型デイサービス「トータルリハセンター」や訪問看護ステーションを設け、地域に根ざした「訪問看護・リハビリテーションサービス」を提供しています。
また介護従事職にご興味のある方も、お気軽にお問い合わせください。


