自宅でできる脳梗塞後遺症の改善リハビリ|口腔ケアの重要性も解説

脳梗塞の後遺症には、病院での専門的なケアに加え、自宅での継続的なリハビリが症状改善に大きく関係することがわかっています。
本記事では、自宅で無理なく取り組める簡単で効果的なリハビリ方法と、専門家のサポートを受ける重要性についてご紹介します。
目次
脳梗塞とは
脳梗塞とは、脳の血管が詰まることで脳の一部に血液が行き渡らなくなり、その部分の脳細胞が壊死してしまう病気で、身体の麻痺や手足のしびれなどさまざまな後遺症が出ることがあります。
脳梗塞の主な後遺症
脳梗塞の主な後遺症は以下の5つです。
- 運動障害:半身麻痺や筋力低下が生じ、歩行困難や日常動作への支障
- 感覚障害:しびれや痛み、温度感覚の低下
- 言語障害:言葉が出にくい、理解しにくいなどの症状(失語症)
- 嚥下(えんげ)障害:食べ物や飲み物を飲み込む機能の低下
- 高次脳機能障害:記憶力や集中力の低下、判断力の衰え

身体的な後遺症により活動量が減少することで、筋力が低下し、寝たきりになる場合もあります。そしてこれらの後遺症は、単に身体機能の問題だけでなく、精神的な面にも大きな影響を与えます。
身体が不自由になったことで自信の喪失やうつ状態、社会的孤立感を抱く方も少なくありません。
脳梗塞後の回復過程
脳梗塞後の回復過程は3つの段階に分けられることが多いです。
| 急性期(発症からおおよそ2週間) | 生命維持と合併症予防が最優先となる時期です。 寝たきり防止のため、ストレッチや機能訓練、嚥下訓練を中心におこないます。 |
| 亜急性期(数週間~6か月) | 脳の可塑性を活かした集中的なリハビリがおこなわれるため、この時期に最も機能回復が期待できます。 発症から約3か月で症状が安定する方が多いのも特徴です。 この時期は、身体機能の回復を目的としたリハビリが中心となり、運動療法や言語療法など、回復した機能の維持を目指す段階です。 |
| 慢性期(6か月以降) | これ以上の自然回復は見込めず、障害の程度が固定される時期です。 しかし、適切な訓練を続けることで、緩やかながら機能改善がみられる場合もあります。 |
周囲のサポートと患者さまのリハビリへの意欲が機能回復に大きな影響を与えます。
自宅でできる効果的なリハビリ方法
病院でのリハビリに加え、自宅での取り組みが重要です。ここでは、自宅でできる簡単で効果的なリハビリをご紹介します。
運動機能改善のためのリハビリ
手足を動かすことで、運動機能や脳の回復が期待できます。
グーパー体操
肩の高さに腕を上げたらひじを真っすぐに伸ばし、手をグーにしたり、パーにしたりを5秒ずつ繰り返します。足の指もグーパーすることで足のリハビリにもなります。
単純な動きですが、脳の活性化、手足の動きや血流を良くするのに効果的です。
座位バランス訓練
椅子に座った状態で、両手を広げてバランスを取る練習をしましょう。この訓練は体幹の安定性を高め、立位や歩行のバランス力改善につながります。
徐々に手を使わずにバランスを維持することや、左右のお尻へ交互に体重をかける訓練もおすすめです。
座ってできる座位体操の効果と方法は以下でも紹介しています▼
足踏み運動
椅子に座った状態でお腹をへこませ、背筋を伸ばします。左右交互に、足を90度になるまで持ち上げて下ろすという動作をおこないましょう。
慣れてきたらリズムに合わせてテンポよく足踏みすると、より効果的です。
壁などの支えを使って、立った状態での足踏みなども、歩行機能の回復を促進します。
日常生活に取り入れるリハビリ
日常の中にリハビリを取り入れることも、後遺症の早期回復に効果的です。
食事の準備
お皿やお箸を並べる、お茶を注ぐなど、簡単な作業をおこなうことで、手先の細かい動きや集中力の訓練になります。

整理整頓
洗濯物を干したり衣類をたたんだりする作業は、認知機能と手先の運動機能の回復を促進する良いリハビリです。
植物の手入れ
水やりや簡単な手入れは、責任感を持つことで心のリハビリになります。

嚥下機能および言語障害のための自宅トレーニング
脳梗塞で半身麻痺になると、嚥下機能や言葉を発する機能の低下もみられます。
嚥下機能や言語障害の改善に効果があるトレーニングをご紹介します。
嚥下機能改善のトレーニング
嚥下機能の低下は、誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)などの深刻な合併症を引き起こす可能性があるため適切なケアやトレーニングが不可欠です。
口のトレーニング
- 口を大きく開けて「あー」と声を出す
- 口を閉じて「うー」と唇を前に突き出す
- 頬を膨らませたり、すぼめたりする
- 舌を前後左右に動かす
のどのトレーニング
- 空嚥下(口の中に何もない状態で唾液を飲み込む)を繰り返す
- 首を前後左右にゆっくりと動かす
- 軽く咳払いをする
- 息がのどに当たるように吸って、三つ数えて吐く
これらのトレーニングを1日に5〜10回程度おこなうことで、口周りの筋肉が鍛えられます。また、嚥下訓練などの他に、歯科医院や専門家による適切なケアも重要です。
たとえば、DSセルリアが運営するトータルリハセンターでは、嚥下機能の改善を含む口腔ケア提供などをおこなうことで、口腔機能のQOL向上を目指します。
また、訪問看護においても、いつまでも食事や会話を楽しむためのお手伝いとして、話す・食べることに関するリハビリをおこなっています。
ご興味のある方はお気軽にお問い合わせ、資料請求をお願いします。
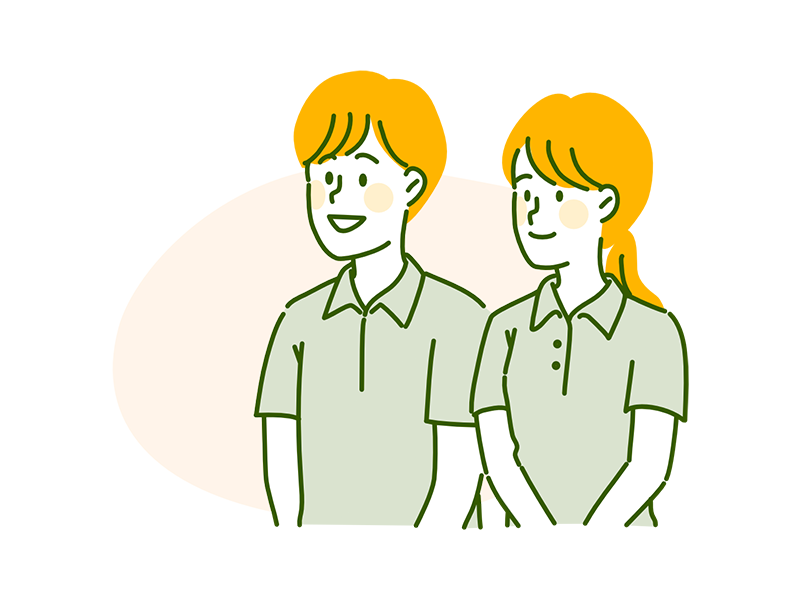
お気軽にお問い合わせください。043-273-5024営業時間 9:30-18:30 [ 土日・祝日除く ]
お問い合わせ・資料請求 お気軽にお問い合わせください。言語機能回復のためのトレーニング
言葉が不自由になると思うように意思が伝えられず、ストレスが溜まったり認知症が進行するなどの恐れがあります。また、脳梗塞後は口の中の環境が変化することが多く、特に嚥下機能の低下は誤嚥性肺炎などのリスクを高めるため、以下のトレーニングを実施しましょう。
【音読トレーニング】
新聞や本を声に出して読むことで、言葉の発音や理解力の向上につながります。
【会話のトレーニング】
ご家族との日常会話を意識的に増やすことが効果的です。
質問に答える、自分の気持ちを表現するなど、コミュニケーションの機会を設けましょう。
【歌のトレーニング】
馴染みのある歌を歌うことは、口を動かす訓練になるため、言語機能回復に効果的です。また、メロディーに乗せることで、言葉が出やすくなるほか、楽しみながらトレーニングをすることができます。

まとめ
脳梗塞後遺症の回復には時間がかかるため、日々の小さな積み重ねが大切です。周囲のサポートと適切なケアが、患者さまの生活の質を高め、笑顔を取り戻す助けになります。
トータルリハセンターでは、理学療法士や作業療法士などのリハビリ専門職が、身体機能向上をサポートします。ご家族だけで抱え込まず、ぜひ専門家のサポートを活用してください。
脳梗塞の後遺症のリハビリには「DSセルリア」
当社では、訪問看護とリハビリ型デイサービスを提供しています。
「トータルリハセンター(TRC)」では、機能訓練などに加え、摂食・嚥下機能訓練や口腔清掃、口腔機能向上のためのプログラムなど多角的に日常生活動作(ADL)の維持・改善に取り組んでいます。
「DS訪問看護ステーション」では、病気や障害のある方が住み慣れた地域や家でその人らしい暮らしができるよう、看護師や理学療法士・作業療法士などが直接訪問して、その人にあった看護やリハビリテーションを提供します。
施設見学・ご相談は随時受け付けております
ご家族の介護に関してお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
DSセルリア株式会社では、東京・千葉エリアにリハビリ型デイサービス「トータルリハセンター」や訪問看護ステーションを設け、地域に根ざした「訪問看護・リハビリテーションサービス」を提供しています。
また介護従事職にご興味のある方も、お気軽にお問い合わせください。


